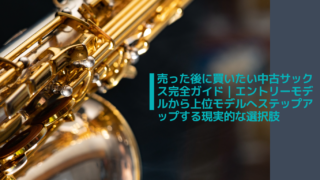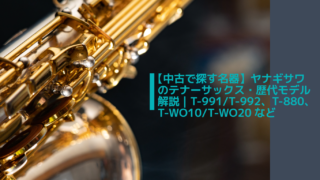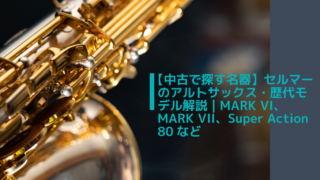毎年11月6日は「サクソフォンの日(サックスの日)」です。これはサクソフォンの発明者、アドルフ・サックス(Antoine-Joseph “Adolphe” Sax)の誕生日に由来します。
サックスは19世紀に生まれて以来、軍楽隊や吹奏楽、そしてジャズやポピュラー音楽を通じて世界中に広がり、独特の存在感で多くの人を魅了してきました。
1. サクソフォンの日(11月6日)とは?
アドルフ・サックスは1814年11月6日生まれ。彼の誕生日である11月6日が「サクソフォンの日」として世界的に認識されています(記念日として扱う国や団体により呼び方は異なりますが、アドルフ・サックスの誕生日を祝う日です)。
2. 発明者アドルフ・サックスと「楽器誕生」の物語
2-1. ベルギーの発明家、アドルフ・サックスの挑戦
アドルフ・サックス(Antoine-Joseph “Adolphe” Sax)は1814年11月6日、ベルギーのディナン(Dinant)に生まれました。子どもの頃から風・金管楽器の工房を営む父親の影響を受け、若くしてクラリネットやフルートの演奏・製作に携わっていました。
彼の目的は、「木管の繊細さ」と「金管の響きを兼ね備えた新しい楽器」を作ることでした。実際、ヤマハの楽器紹介でも、「彼のアイデアは木管楽器の良さと金管の良さを融合させるものであった」と示されています。1842年にはパリへ移り、そこで自身の工房を構えて本格的に製作活動を開始。1846年6月28日にはサクソフォンの特許を取得し、新たな管楽器ファミリーとして世に送り出しました。しかし、特許申請後も模倣品、訴訟、資金難など多くのトラブルに見舞われ、彼自身は晩年破産を重ねることになりました。
このように「一発発明ではなく、多くの挑戦と改良を重ねた発明家の物語」が、サクソフォン誕生の背景にあるのです。
2-2. 金管と木管の“架け橋”として生まれた楽器
サクソフォンは、従来の木管楽器(クラリネット・フルート)と金管楽器(トランペット・ホルン)とを橋渡しする設計がなされていました。例えば、金管楽器の素材である真鍮(ブラス)を用いながら、クラリネットと同じようにリード(簧)を使用して吹奏される形式です。ヤマハの楽器紹介では「金管の強い響き、木管の運指性を併せ持つ」と説明されています。
発明当初、サクソフォンは複数のサイズ(ソプラノ〜コントラバス)で設計されており、初期特許でも「8〜14種類」のサイズの楽器を想定していたとする資料もあります。軍楽隊などでの採用においても、「木管の柔らかさ+金管の音圧」というメリットが重視されました。例えば、ベルリオーズも当時の新楽器を称賛しています。
こうして、サクソフォンはその構造上「木管の演奏性」と「金管の響き」を兼ね備えた“架け橋的な楽器”として、19世紀中盤から徐々に普及を始めることになります。
2-3. 初期の批判と受容──軍楽隊・吹奏楽での普及
とはいえ、発明直後のサクソフォンがたちまち正統派のクラシック音楽で使う楽器として受け入れられたわけではありません。実際、多くのクラシック音楽関係者からは異端視されたという記録があります。「金管と木管の中間」という設計が、従来の楽器分類に馴染まなかったためです。具体的には、楽器雑誌 TIME では「真面目な音楽にとってサクソフォンはシンデレラ的な存在だった」との記述があります。
一方で、フランス軍楽隊を中心に採用が進み、サックスのファミリーの中から特にアルト・テナー・バリトンが「E♭/B♭系」で標準化され、吹奏楽や軍楽の世界で定着しました。
そして20世紀初頭、アメリカのジャズやビッグバンドではサクソフォンがソロ楽器として爆発的に人気を博し、今日の音楽シーンにおける「サックス=ソロ楽器」という位置付けを確立しました。
このように、初期の「批判・拒否」から、「軍楽・吹奏楽への採用」「ジャズでの躍進」という3段階を経て、サクソフォンは世界的な楽器として地位を築きました。
3. サクソフォンの種類と用途 — ソプラノからバリトンまで
3-1. ソプラノからバリトンまで──音域と用途の違い
サックスのファミリーには多様な種類がありますが、実際に一般的に使われている主な機種は以下の通りです。
- ソプラノ(Soprano)
- アルト(Alto)
- テナー(Tenor)
- バリトン(Baritone)
これらは音域・サイズ・用途がそれぞれ異なり、演奏シーンや買取時の価値にも影響します。
ソプラノは最も高音域で、機体も比較的小型・軽量ですが、演奏・管理には繊細さを要します。
アルトはE♭キーの中で最も使用頻度が高く、初心者からプロまで幅広く使われています。
テナーはB♭キーで、サイズも少し大きくなり、深みのある音色が特徴。ジャズやポップスで人気があります。
バリトンはE♭キーで、最も低音域に位置し、サイズ・重量共に“大型楽器”として位置づけられ、吹奏楽やビッグバンドでの低音を支える楽器として活躍します。
3-2. ジャズ・吹奏楽・クラシックでの代表的な使われ方
サックスという楽器はジャンルや用途によって使われ方が大きく異なります。以下に主な代表用途を整理します。
- クラシック/吹奏楽・コンサートバンド
吹奏楽やコンサートバンドではアルト・テナー・バリトンが主として使われます。編成としても“アルト2本+テナー1本+バリトン1本”などが定番となることが多く、曲によってソプラノがソロや特定の編成で使われることが多いです。 - ジャズ・ビッグバンド・ポップス
ジャズ、特にカルテットやクインテットでは、テナーもしくはアルトがメインのソロ楽器として強く場面で使われてきました。特にテナーは多くのジャズ巨匠が用いた楽器として「サックス=テナー」の印象を創出しています。ビッグバンドではアルト・テナー・バリトンが必ず使われ、曲によって持ち替えでソプラノを使います。ポップスでは、アルトかテナーが、トランペットやトロンボーンとともにホーンセクションとして使われることが多いです。 - ソロ・室内楽・現代音楽
サックスはその歴史からクラシック曲での活躍は近年の曲に限られます。その中でソプラノは、高音域と表現力から現代音楽のソロや室内楽で採用されることがあり、バリトンは編成において低音域の支えとして“陰の主役”的な役割を担うことがあります。しかしながら、評価される演奏現場は他の管楽器に比べると限定的です。
3-3. 現代の人気ブランドと名機(セルマー・ヤマハ・ヤナギサワ)
サックスの種類を理解したうえで、主要ブランドとその名機にはどういうものがあるのでしょうか。以下は種類別に“人気が高いブランド/機種”の一例です。
- セルマー(Selmer Paris)
世界的にもブランド認知が高く、特に「スーパーアクション80シリーズII/シリーズIII」などはアルト・テナーともに高評価を受けています。ソプラノ・バリトンも限定モデルとして流通しています。 - ヤマハ(Yamaha)
中級〜上級機種において信頼性の高い仕上がりを見せており、「YAS-875EX(アルト)」「YTS-875EX(テナー)」などが名機とされ、ブランドとしても安心感があります。 - ヤナギサワ(Yanagisawa)
国産のプロモデルブランドで、精密な作りと響きのまとまりに定評があります。特にWOシリーズ(WO10/WO20)はアルト・テナーを中心に人気で、ソプラノ/バリトンでも流通が増えています。
例えば、ヤマハ公式サイトでは「Soprano to Baritone — the saxophone family currently in widespread use」として紹介しており、ソプラノ・アルト・テナー・バリトン全体の構造・用途の差を丁寧に説明しています。
4. 日本でのサクソフォン文化 — 吹奏楽の隆盛と学校教育
4-1. 吹奏楽文化と学校教育における普及
日本において、サックスの普及を語る上で欠かせないのが学校教育と吹奏楽部活動の広がりです。
明治時代以降、洋楽器が音楽教育に取り入れられ、吹奏楽も発展してきました。例えば、東京藝術大学(旧東京音楽学校)の管・打楽器課程にはサックスも含まれており、1930年代から本格化しています。
また、全国吹奏楽コンクールのような大会が毎年実施され、学校の吹奏楽部でサックス(特にアルト・テナー・バリトン)が編成の中でも重要ポジションとして定着。これにより、楽器の在庫数や流通量も増えています。
4-2. 国内プレイヤーの活躍と音楽シーンへの影響
日本のジャズ・ポップス・クラシックのシーンにおいては、サックス奏者の活躍は大きな影響を与えてきました。
たとえば、ジャズサックス奏者の渡辺貞夫(Sadao Watanabe)は、戦後日本におけるジャズの重要人物の一人であり、サックスという楽器の認知を大きく引き上げた存在です。[出典:Japan Times記事「Sadao Watanabe, Japan’s godfather of jazz, passes on his wisdom」](https://www.japantimes.co.jp/culture/2019/06/25/music/sadao-watanabe-japans-godfather-jazz-passes-wisdom/)
加えて、国内作曲家によるサックス作品の創作も増えており、たとえば野田燎(Ryo Noda)は、クラシック・サクソフォン作品の国際的な評価を高めた日本人作曲家の一人です。[出典:Wikipedia “Ryō Noda”](https://en.wikipedia.org/wiki/Ry%C5%8D_Noda)
これらの活躍がサックスの専門奏者人口や興味の裾野を広げ、買取・流通市場においても「プロユースモデル」「ハイエンドモデル」への需要を支える基盤となっています。
4-3. サックス人口の増加と中古市場の盛り上がり
日本国内では、吹奏楽部や軽音部、アマチュアバンドなど、サクソフォンを手にするプレイヤーの数が年々増加傾向にあります。専門的な楽器店や中古楽器市場でも、サックス(特にアルト・テナー)を売りたい・買いたいという動きが活発化しており、「使わなくなった楽器を手放す」「初心者・再開者が手に入れる」という二つの売買層が生まれています。
このような背景により、買取業者でもサクソフォンの査定・買取案件が増加しており、モデル・状態・付属品次第で価格が大きく変動する“活発な中古市場”が形成されています。また、希少モデル(ソプラノ・バリトン)やハイグレードモデルは流通量が少ないため価格が下がりにくく、改めて価値が見直されるケースもあります。
5. サックスをもっと楽しむための3つのヒント
5-1. 初心者でも始めやすい理由
サックスは一見すると難しそうな楽器に見えますが、実は初心者でも始めやすい楽器のひとつです。その理由は、「音が出やすい」「運指がシンプル」「幅広いジャンルに対応できる」という3点にあります。特にアルトサックスは、吹奏楽やジャズ、ポップスなど幅広い場面で活躍でき、身体への負担も比較的少ないため、初めての管楽器としても人気です。
また、最近ではネット動画やオンラインレッスンが充実しており、自宅でもプロのレッスンを受けられる環境が整っています。「楽器を始めたいけれど難しそう」と感じていた人でも、11月6日の“サクソフォンの日”をきっかけに新しい趣味としてスタートしてみるのもおすすめです。
5-2. 楽器を選ぶときのポイント
サックスを選ぶ際に大切なのは、自分の演奏目的と予算に合ったモデルを選ぶことです。たとえば、これから始める初心者であれば、扱いやすいアルトサックスが最適。上達して本格的に演奏を楽しみたい人は、セルマー「シリーズII」やヤマハ「カスタムシリーズ」のような上位モデルを検討してもよいでしょう。
中古市場でも、メンテナンスの行き届いた楽器であれば新品に近い吹奏感が得られるものも多く存在します。購入前には、実際に試奏できる店舗や専門スタッフのいる買取・販売店を訪ねてみると、自分に合ったサックスが見つかりやすくなります。
5-3. 使わなくなった楽器の新しい活かし方(買取・再利用)
サックスを吹いたことのある人の中では、学生時代や趣味で使っていたサックスを長くケースに眠らせているケースも多いのではないでしょうか。実は、サックスは状態が良ければ高額での買取が期待できる楽器の一つです。
とくにセルマーやヤマハ、ヤナギサワなどの人気メーカーは中古市場での需要が高く、モデルによっては購入時に近い価格で取引されることもあります。また、最近では出張買取や宅配買取など、自宅にいながら簡単に査定できるサービスも増えています。
もし再び演奏する予定がない場合は、専門店に査定を依頼して次のプレイヤーへと橋渡しするのもひとつの方法です。眠っている楽器が、誰かの新しい音楽人生を支える——そんな素敵な循環を生み出せるのも、サックスの魅力といえるでしょう。
6. サクソフォンの日をきっかけに広がる文化とコミュニティ
6-1. SNSで盛り上がる「#サックスの日」キャンペーン
毎年11月6日になると、SNS上では「#サックスの日」「#サクソフォンの日」などのハッシュタグがトレンド入りします。プロ奏者から学生、アマチュア愛好家まで、演奏動画や愛用楽器の写真を投稿し、世界中のサックスプレイヤー同士が交流を楽しむ1日となっています。
特にX(旧Twitter)やInstagramでは、セルマーやヤマハといったメーカー公式アカウントも参加し、フォロワー限定のキャンペーンやフォトコンテストを開催する例も見られます。こうした動きは、演奏人口の裾野を広げるだけでなく、音楽文化としてのサクソフォンの魅力を再発見する機会にもなっています。
6-2. 国内外のサックスイベント・フェスティバル
日本国内では、ジャパン・サクソフォーン・フェスティバル(主催:日本サクソフォーン協会)や東京国際バリトンサックス・フェスティバルといったイベントが毎年行われています。特に、ジャパン・サクソフォーン・フェスティバルでは、ワークショップやマスタークラス、試奏会なども同時に開催され、初心者から上級者までが交流できる場となっています。
また海外では、ベルギーのディナン(Dinant)で行われる「Adolphe Sax International Competition」が有名です。これはサクソフォンの発明者アドルフ・サックスの出身地で行われる国際コンクールで、クラシック界の登竜門として知られています(参考:https://www.adolphesax.com/)。
6-3. サクソフォンを通じて広がる仲間と文化
サクソフォンはその表現力の豊かさから、ジャンルや世代を超えて人々をつなぐ楽器です。学校の吹奏楽部や社会人ジャズバンド、地域のアンサンブルなど、サックスを中心としたコミュニティは全国に存在します。
オンライン上でも、「サックス愛好会」や「Saxophone Players Japan」などのコミュニティが活発に活動しており、練習方法の共有や中古楽器の情報交換などが盛んです。
11月6日の「サクソフォンの日」は、こうしたつながりを再認識し、自分の音楽活動を振り返る絶好のきっかけです。楽器を持っていない人も、この日を機に音楽店や中古楽器サイトを覗いてみると、新しい出会いがあるかもしれません。
まとめ|11月6日は“音楽をつなぐ日”としてサックスを楽しもう
サックスは、クラシックからジャズ、ポップスまで幅広く愛される楽器です。その魅力は、音色の豊かさだけでなく、演奏を通じて人と人をつなぐ力にあります。発明から約180年を経た現在も、サックスはその独特な表現力で世界中の音楽シーンを支えています。
11月6日の「サクソフォンの日」は、演奏者もリスナーも関係なく、“音楽を楽しむすべての人”が主役になる日。これを機に、サックスを始める人、再び手に取る人、あるいは楽器を手放して次の誰かに託す人——それぞれが音楽と向き合うきっかけを持てる日になるでしょう。
もし眠っている楽器があるなら、買取査定を通じて再び誰かの手に渡すのも立派な「音楽のバトンリレー」です。あなたのサックスが、また新しい音を奏で始めるかもしれません。
🎷 あなたのサックス、今いくら?
使わなくなった楽器も、新しいプレイヤーの手に渡ればまた輝きます。買取相場を知りたくなったらこちらをチェック✅ → 【2025年最新版】サックス買取相場を徹底解説!メーカー別・状態別の高額査定ポイント
参考・出典(主要な参照元)
- Adolphe Sax — Britannica biography. (Adolphe Sax の生涯・発明について)(https://www.britannica.com/biography/Antoine-Joseph-Sax)
- Adolphe Sax & Cie — 公式/記念サイト(https://www.adolphesax.be/en/adolphe-sax/)
- Saxophone — Britannica (楽器史・軍楽隊での採用など)(https://www.britannica.com/art/saxophone)
- Yamaha — “What’s the difference between soprano, alto, tenor and baritone saxophones?”(https://hub.yamaha.com/winds/wood/whats-the-difference-between-soprano-alto-tenor-and-baritone-saxophones/)
- National Saxophone Day — National Day Calendar(https://www.nationaldaycalendar.com/national-day/national-saxophone-day-november-6)
- 日本の吹奏楽史関連(書籍)『日本の吹奏楽史 1869–2000』ほか(https://amzn.to/3WGTDVi)
- History / patent note — Wired article on patent (1846)(https://www.wired.com/2010/06/0628saxophone-patent)